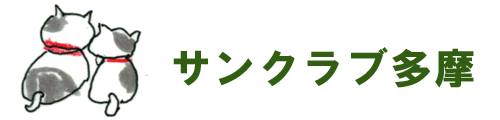8月の活動
8月12日(火)集いの会
先月は入院中のお子さんの「退院後のことで忙しくしていて来れなかった。」という方が「子供が退院して自宅に帰っても、今日は主人が家にいてくれるので来れた。」とこれまでの経過を嬉しそうにお話しくださいました。病院の相談員さんのアドバイスによって、自分で調べた24時間(夜間は電話対応)の訪問看護の事業所がとても良くて「安心していられる。」とのことでした。
ご主人の健康状態に不安が続く別のご家族は、検査の結果がまだ出ないけれど、「結果を聞きに行くときは子供も同席させる」とご主人がおっしゃっているそうです。「悪い方へ進みそうで、ますます先のことが不安になる。」と顔を曇らせていました。集いの会で気兼ねなく本音で話せることで、気持ちが少しでも軽くなることを願うばかりです。
(S.T)
紹介します! 最近出版された「おススメの本」
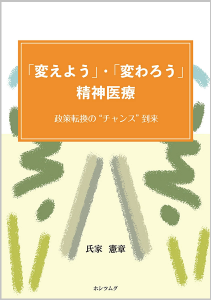
「変えよう」・「変わろう」精神医療
政策転換の”チャンス”到来
著者 氏家 憲章
発行 ホシツムグ
みなさんは「精神医療は政策転換が避けられない事態」と聞いて信じられますか?
今、医療現場では大きな変化が起きています。なぜ、日本は政策転換(改革)が進まないのでしょうか。その原因を精神医療政策の歴史を振り返って考えてみませんか。
〈定価 本体1,000円) 入院中心の精神医療から 地域中心の精神医療へ
7月の活動
7月8日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
古くからの会員で久しぶりに参加された方がいらっしゃいました。ご主人の体調不良のためにストレスが溜まるばかりなので、今日はいろいろ聴いてもらいたくてやってきました、とのこと。ご主人には手がかかるけれど、日々の暮らしの中で病気のお子さんが、なにかとお母さんを手助けしてくれるそうです。聴いていた周りの人たちは、そこのところがうちとは違う、とそれぞれの家族の食事風景や家事の分担などを話し合いました。
(S.T)
7月23日(水) 学習交流会
地域活動支援センター「のーま」について学ぼう!
出席者7人(うち会員6人)
親の高齢化に伴い、会員から当事者の居場所や相談先等についての悩みが寄せられることも増えています。そこで、7月の学習交流会は、聖蹟桜ヶ丘駅近くの健康センター4階にある、障がい者支援事業を展開している「マルシェたま」から、社会福祉士・公認心理士として相談・支援等に奔走されている小川肇さんをお招きし、お話を伺いました。
◆マルシェたまの3つの事業について
<①多摩市地域活動支援センター のーま>
- 多摩市在住の障がいのある方が対象で、手帳の有無は問わない。
- 病院の診断を受けてもらって、医療の判断後の利用、支援になる。
- 利用者は、精神疾患の方が6~7割、知的障害の方が2割、1割程度が身体障害という状況。
- 利用は登録制。相談は無料だが、プログラムや交通費では実費負担あり。
- 福祉に係る様々な相談に対応(内容によって他機関と連携して支援する)
- 福祉サービスや医療サービス利用の支援
- 家族や友人との人間関係
- 生活に関わる支援
- プログラムの実施(運動、創作、調理、音楽、トーク等、年1回外出プログラム)
- 人気はフィットネス、かんたんダンス、ナイトプログラムもあり。
- 毎月末に登録者に、月間予定表を送付・配布している。面談をした うえで登録前の見学が可能。一部事業を除き、プログラムの参加予約が必要ないので利用しやすい。
- フリースペースの利用(パソコン、図書、談話室利用)
<②マルシェたま障害者相談事業所>
- 障害者総合支援法に基づく計画相談機能
- 福祉サービスの案内・調整(サービス等利用計画の作成)を行う。
<③多摩市障がい者就労支援センター なちゅーる>
- 多摩市の独自事業。登録対象は多摩市在住の障がいのある方。ただし、障害者就労は、手帳のある方が対象となる。ハローワークのような仕事のあっせん(紹介)はできない。就職を希望される方への準備支援、就職した方への定着支援及び生活支援、会社の方への雇用主支援を行う。
- 相談は無料。
- 現在、精神障害、知的支援の方の登録が半々ずつで、最近は高次脳障害のような身体障害の方も登録している。発達障害からうつ病を発症するケースも多く、障害をどう受容するかが重要なポイントとなっている。
- 就職までのステップを一歩一歩確認しながら、一般就労に向けて支援をする。
- 就労を継続していくための生活支援や講座、交流会も実施している。
◆懇談を通して
マルシェたまについての説明後は、小川さんを囲んで懇談です。コロナ後のここ1~2年で20代前半の方の相談が一気に増加しているそうです。これまで築き上げてきた人間関係がコロナでくずれて精神疾患になったというケースが多いようです。また、親の高齢化に伴い、いわゆる「80・50問題」の相談も多くなってきていて、ニュータウンという地域性もあるのか、近隣の八王子市も同じような傾向だそうです。
市役所の障害福祉課に行くと、地域活動支援センターとして「あんど」「のーま」が紹介されますが、「あんど」は身体障害、身体の高次脳障害、高齢者の登録が多い傾向に対し、「のーま」は精神障害の登録者が6~7割を占めているそうです。本人の希望にそって見学・体験もでき、それからサービス利用をする場合は、認定調査で受給者証をとる支援もしているそうです。
最初の一歩は、本人とご家族が一緒に行って、「のーま」に登録してもらう。基本は本人の意思です。本人だけ、ご家族だけでの登録手続きも可能だそうです。病院のデイケアに比べ、より緩やかな利用ができるので、作業所に行く前のプロセスにする方が多いそうです。
参加者からは「50代の子どもが家から出てプログラムに参加してもらうのにどうしたらいいか?」という悩みや、精神障害を抱えての就労の継続についての質問が出されました。また、グループホームについては、生活自立を目指す通過型は若い方が対象で、滞在型の精神障害者のグループホームは限られることにも言及されました。小川さんは、家に引きこもっている方へは、自分たちも悩みながら、まず訪問看護を紹介して、場合によっては同行する、家に来るのが嫌なら公園等の外で会う等の対応もしているが、アウトリーチの難しさがあるというお話でした。多種多様な相談に、調べて勉強しながら、また他の様々な専門機関等とも連携して対応しているそうで、厳しい現実もあることを踏まえながらも、何とかしたいと奮戦している様子が、温かく穏やかな口調から伝わってきました。
「のーま」は、ふらっと50歳代の方でも行くことができるので、作業所に通っている40歳から50歳代のでは方の利用も多いということです。登録者には担当の職員が付くことも、利用者には安心材料なのかなと感じました。14名の職員の皆さんが、マルシェたまの事業全体で、千名に迫る登録者の対応をされていらっしゃるとのこと。当事者の意思に寄り添った柔軟な運営を目指しているマルシェたまの情報が当事者に届くことを願いながら、懇談は終了しました。
(M.F)
6月の活動
6月10日(火)集いの会
出席者5人(うち会員5人)
今月の高森先生個別相談に行った方がいたので、「どうでしたか?」と聞くと「初めて先生にお会いしたけれど、行って良かったー。ためになった。」ということでした。以前相談に行った方からは「私は先生の言葉にすごく救われたの。」と話していました。
精神の病気は春先に調子を崩す人が多いようで、「今やっと少し落ち着いたけど、ちょっと前はいろいろたいへんだった。」という話がたくさん出ました。
(S.T)
6月19日(木)東京つくし会評議員会
参加者1名
会場は調布市文化会館(たづくり)8階映像シアターでした。
照り返しの強い真夏のような一日でした。46名(出席者42名+委任状4名)の家族会の参加があり、過半数を超えており、会の成立が宣言されて議事に入りました。
真壁会長の挨拶があり、「つくしんぼ」斉唱、来賓挨拶では自民党・公明党議員そして手をつなぐ育成会理事の方が挨拶をされました。共産党からは祝電をいただきました。
議事に入り、麦の会の富岡さんが議長に選出されました。
第一号議案 2024年度事業・活動報告 植松副会長(シュロの会)より報告されました。
- 滝山病院は、11月から希望の丘八王子病院と改名され、外来患者を受け入れるようになり、看護師の常勤化、建物の改修工事も進み、少しずつ生まれ変わろうと努力しているようであるが、今後も見守る必要がある。
- NHKの精神障がい者及び家族の現状や課題に対するアンケートに企画協力し、精神障がい者を支える家族の重い負担の実態と、家族の高齢化問題、地域で支えていく体制の脆弱さ等をテレビでアピールした。(560通のうち360通の回答があった。64%)
- 財政問題 昨年度に引き続き収入関係では、登録会員が減少傾向にある。このままの状態が続くと会の運営に支障が出る事が考えられる。会の高齢化等による会員減少がある。つくし会全体として考える必要がある。
第三号議案 2025年度事業・活動計画案 植松副会長から提案されました。
- 2025年4月より、JRグループと大手私鉄16社が揃って精神障がい者の運賃割引を導入した。やっと身体・知的障がい者と同じ地点に立てた。この成果に確信を持ち、今後はすべての手帳所有者が割引対象となるように改善を求めていく。
- 今後もピア活動の充実に取り組む。
- 地域生活を支援する多職種チーム「アウトリーチ」の数を増やし、支援者の研修の充実、身近な窓口で相談でき、必要なサービスに繋げられる体制づくりを求めていく。
※第一号議案から第五号議案まで、すべて承認されました。
午後からは、以下の講演会がありました。
「看護職からみた精神科医療のこれから ~入院中心医療から地域医療を目指して~」講師 草地 仁史(くさち ひとし)氏 一般社団法人精神科看護協会 業務執行理事 政策企画局 局長
(T.M)
6月21日(土)豊田先生の交流会
5名(会員5名)
梅雨の晴れ間とは言い難いほどの暑い日で、今までになく参加者が少ないのも「会員が高齢化している中で熱中症を警戒してのことかな。」と思うような日でした。
豊田先生は、昨年末から続いたご自身の体調不良や入院中のお母様の逝去と葬儀等一連の事務処理などで、かなりたいへんな半年を過ごされたようでした。
また、ご実家の近くで依存症の施設を作りたいという方からの協力を求められている、というお話もありました。
今回は豊田先生の講義は無かったので、参加者一人一人の話に移りました。
後期高齢者になってあちこち具合が悪いが、友人と集まると病気の話で盛り上がる、との話には参加者一同の共感が得られました。
役員の一人が、公的機関に家族会との懇談を電話で申し込んだところ、依頼書を出すように言われてファックスで送ったのに3回目の電話で断られて、「自分のやり方が悪かったのでは。」と落ち込んだことを話しました。それに対して豊田先生から、公的な場所が依頼書を出してほしいというのは内諾の意味なので、その後断ってくることがおかしいと同調してくださいました。その後の対処方法などのアドバイスもあり、再挑戦する勇気が出ました。
古い会員から、「昔はほんとうにたいへんだったのに、今は病気の子どもも自立して、楽になって猫と暮らしている。」という話があり、一同感嘆のため息がもれました。
職場の仲間に、食後の洗い物が心の負担になっていることを話したら、「食器は家族それぞれ自分の分を洗う。」と言われて、家でそう話したら、快く了承してくれて気持ちがとっても楽になった、という話から、食洗機のことまで話が及びました。
最近入会された方からは、家族構成と、どうして入会されたかの話があり、会終了後の個別相談を受けて帰られました。
(S.T)
5月の活動
5月13日(火)集いの会
参加者4名(うち会員4名)
息子が作業所でトラブルになったことで悩んでいたら、作業所の所長が支援センターに連絡してくれて、話し合いが持たれたとの報告がありました。参加したのは本人と母親、作業所、支援センターの4者です。その場で、本人の話をじっくり聴いてもらえて本人も納得したようで、違う作業所に行くことになったそうです。
その後で、参加者それぞれの地域の支援センターがどこにあり、どんなことをしてくれるのかを皆で話し合いました。
(S.T)
5月24日(土)2025年度通常総会
出席会員23名・来賓2名
62名の会員中、23名出席、委任状26名で、総会が成立したことが宣言され、会員の中から議長が指名され、以下5件の議案審議に入りました。
<第1号議案「2024年度活動報告」について>
賛成多数で承認
<第2号議案「2024年度決算報告」について>
収入と支出の主な内容についての報告に続き、監査からの報告。賛成多数で承認。
<第3号議案「2025年度の活動計画及び予算案」について>
賛成多数で承認。
<第4号議案「サンクラブ多摩会則」の改正について>
会則の全面改正の提案。賛成多数で承認。
<第5号議案「役員の選任」について>
改正された会則及び細則に基づき、8名の役員を選任。賛成多数で承認。
(M.F)
4月の活動
4月5日(土) 高森先生の公開講演会
「みんなでやろう 家族SST(第65回)
参加者 36名(うち会員15名)
◆「バイバイ ブロンディ」の歌と手話で開会
会場の後の隅にあった電子ピアノを見つけた高森先生が、開会前、急遽、そのピアノを弾き始めました。初めて参加の方も多く、会場の皆さんは、あわててみんなで椅子を180度回転させてピアノを弾く先生の方に向きを変え、「バイバイ ブロンディ」という歌を合唱することになりました。アメリカの新聞連載の4コマ漫画がアニメ化されて人気番組になったのですが、その主題歌がこの歌です。先生は歌と、歌詞を表す手話を参加者に紹介し、その後、先生の弾くピアノに合わせて、みんなで手話を使いながら合唱する展開になりました。その歌は、外の世界に飛び出して行こうとするブロンディへの成長に対する応援歌です。先生は、歌詞にでてくる「I love you so」が大事と、指文字をつくり、「あなたを愛している」という思いが家族に伝わるように行動を変えていく、認知行動療法SST(social skiiis training)に結びつけて説明されました。
まず、親が行動で当事者である子どもに「I Love you」を表すことで、親の気持ちが変わってくるというのが、認知行動療法の基本で、親が変わると、子どもが安心して変わってくるという事にふれました。愛を伝えると子どもは安心し、外に向かうエネルギーが生まれてくるということを、親同士が大きな声と手話で「I love you」と歌うことで、SSTの実践とその意味を提示してくださったプログラムでした。
ちなみに手話では、小指を立てて「I」の指文字・親指と人差し指を立てて「L」の指文字 ・親指と小指を立てて「Y」の指文字になり、3本の指をまとめて立てるので「I love you」を表すサインになります。
◆認知行動療法とは
続いて、ある事例の話です。大学の時にいつもの自分と違う自分に気づき、自分を変えなければと卒業後、一人でロンドンの友人の所に行き、統合失調症を発症した女性の話です。大使館からの連絡を受けて父親が迎えにいったところ、父親を嫌い母親が迎えにくると思っていた娘さんは、幻視もあり父親を認識できない状態で、羽田から大学病院に直接搬送されて入院。母親は入院当日から連日、病院に通いつめましたが、全然よくならず1か月経ってもボロボロの状態。子どもに対する不信感が生まれ、「娘さんを愛してますよね?」と聞かれても答えられずに、自分の中に無意識に「娘が家に不幸を持ち込んだ。これからどうなるのか」というおそれ、怒りと憎しみの気持ちがあるのに気づいたそうです。
「元の自分に戻りたい」という母親からの電話相談を受けた高森先生は、まず、親が「I love you」と娘さんに伝えることが大切であり、心はどうあっても、行動が先で感情は後からついてくるものであり、行動することで親自身の心が変わってくるということを伝えたそうです。家庭内で「I love you」を言葉や態度で表すことは、親自身が変わる行動であり、親が変わることで、子どもが変わりやすくしてあげる方法が行動療法です。親が元気でにこやかであれば環境が良い状態で、環境が良ければ子どもは成長してくるというのが、先生からのメッセージです。
◆引きこもりについて考える
また、先生はブロンディの歌とは真逆の事例に触れました。「家が温かいから、子どもが家から出ない。だからスパルタで教育する」と主張する、戸塚ヨットスクール的な考え方の家族のケースで、その息子さんは、家を出る時は救急車だったということです。そして、高森先生がいつも引き合いに出されるイタリアの精神医療の大改革者のバザーリア先生の次の言葉を紹介されました。
◆当事者に寄り添う事と生活臨床
狂気はどうして生まれるのか。職場や家族などの周りの環境から受けるストレスによって生まれるということを基本に、引きこもりを捉える必要があるということです。初発の患者を拘束し、医療がよけい病気を悪化させる現実にも言及されました。
また、家に引きこもり大声を出されると、親は困って抑えつけようとしがちですが、「大声を出したいのは吐き気と同じ。吐き気は抑えるとよけいに気持ち悪くなり、具合も悪くなるから、吐いても迷惑をかけない大丈夫な場所で吐き出せるようにしてあげるのが適切な対応」とユーモラスに話され、二人の精神科医の言葉を紹介されました。元都立多摩総合精神保健センター長の伊勢田堯先生は、「大声は狂気を発散する。大声で身近にストレスの発散ができる」と、神田橋條治先生は、「大声を出した方がいい。他人に迷惑を掛けずに大声を出すのが、本人にとって一番救われる」と言われたそうです。
この話で、以前のSSTの「お困りごと相談」の高森先生の回答を思い出しました。大声が外に漏れない壺が数千円でネット販売されているのでうまく活用するという助言でした。今回紹介されたのは、夕方にストレスがたまるので、近所の方が「何かおめでたいことでもあったかな」と思うような明るい言葉(例えば「ブラボー」「万歳」など)を、家族全員で晴れやかに唱和し、その後で当事者を相手に話し合うなどの対応です。他にも、カラオケで歌う、打楽器を演奏する、逆に思い切り脱力するなどのストレス発散方法が効果的だそうです。いずれにしても、当事者の気持ちを否定しないで、どうやったら叶えられるかという視点と、明るい家庭環境がポイントだと感じました。
会場に向け、「子どもに死にたいと言われて困ったことのある方は?」と問いかける先生の声に手を上げる方が多く、先生からは「『死にたい』は、『本当は死にたくない』の裏返し」という解説がありました。「死にたい」をずっと家族が聞き続けるのも難しいので、「死にたい」という時は、「言うな」と止めずに、家族みんなで死んでみようと床に寝そべり、「死んだ~」と唱えてみるというのが、先生のお勧め対応策です。「死にたい」というのは、色々と話を聞いて「死なないで」と言ってほしい、「私の気持ちをわかってほしい」ということなのです。家族は当事者の気持ちを聞くよりも説得に力が入ってしまうので、このような脱力的な対応で家族とのつながりを感じてもらうのも、妙案だなと感じました。
高森先生は、「統合失調症の人は、生まれつき敏感に生まれてきたので、ドーパミンが出過ぎて脳に刺激がいく。ドーパミンが出過ぎると、成長するにつれて、社会が広がり情報が入りすぎて、刺激に直にさらされている状態で、脳が疲れていると、五感すべてが敏感に反応してしまう。お薬は、その敏感さ(刺激)を遮断するものであるが、現状では病気そのものを治す薬はない」と、情報提供されました。
親は自分以上のものを子どもに求め、期待から発する言葉で、当事者にストレスを与えてしまう。子どもは親の心の中にある無意識の偏見にも敏感で、親の気持ちを感じ取り、自分自身を嫌いになってしまう。それがストレスになる。東大のSSTの研修では、当事者は、最前列に素裸でみんなに見られながら座ることを余儀なくされているよう感じているとのお話があったそうです。
ある家族会で、「生活臨床」という人間観・哲学的視点での治療研究をされている伊勢田堯先生を呼んで講演をしてもらったところ、「難しくてよくわからなかったが、何か大事な事を言っているようだ」との会員の反応で、高森先生も加わって、再度、講演会を開催したとのこと。その時の親からの困りごと相談に、伊勢田先生は「生活を見ずして治療はできない。どう直すかでなく、どう生きるかだ!」という考え方を提示されたそうです。生活臨床とは、病気そのものを治すというより、患者のストレスに着目し、どうやって当事者が生きていくか、エネルギーを持つことができるかという観点で、生活そのものを見て、ストレスの原因を見つけリカバリーの支援をしていく治療技法だそうです。「親がこうなってほしいと口で治そうとしても、かえってこじれて悪くなるので、元のストレスを無くさなければ駄目だ」という伊勢田先生のお話だったそうです。
高森先生は、「皆さんにストレスを与えない親になってほしい。親は、状況変化に弱い子ども、安心が欲しい子どもを理解しないで、普通の人のような変化を求めるが、本人が思っていることと家族の思っていることは違うという事実を受け止め、本人の気持ちに寄り添ってほしい」と伝えられました。
生活臨床の説明は、次の内容でした。病気の根底には、①生活上の諸課題(金銭・異性・プライド・身体的健康)と、②家族史的課題の2つが存在している。①のどれかが行き詰まるとストレスから病気の症状が出る。②は代々の家族の歴史から培われた文化が当事者に色濃く反映して発症する。人生が行き詰まるから精神症状が発生するので、本人のやりたいという意識を実現するために、実際の生活で支援していくというものでした。実際の治療はオープンダイアログ(患者・家族・支援者で定期的に対話を重ねていく)と同じようなプロダクションという手法によるもので、「病気を治すというのでなく、1回限りの人生をどうやっていくか、幸せな人生を支援する」という哲学が基本にあります。
◆状況変化に弱い当事者とのコミュニケーション
状況変化にストレスを感じる当事者とのコミュニケーションは、まず、胸の中を当事者と同じ状態にして話すこと。アドバイスはその後で。考えが一致していなくても、相槌だけでいい。相手と同じ言葉をくり返す。家の中で大事を起こさないためには、別の惑星の人と話していると思い、自分の考えを言ったり説得したりしないで、まず当事者と同じ言葉を使って共感してあげる。当事者は敏感ですぐに傷つくので、こちらの考えをすぐには言わない。命令的な態度や会話で対応はしない。何よりも、当事者が家族に望んでいることの1番目は、「もっと私の事をわかってほしい」なのです。
講演後に参加者からの相談事に対して、先生からの助言がありました。時間の関係で二つの相談に答えていただいたところで会場を閉める時間になり閉会。その後は、廊下の談話コーナで、高森先生は、お困りごとを相談される方に対応されていました。
(F.M)
4月8日(火)集いの会
参加者4人(うち会員4人)
日々の暮らしの中で、親の体調不良が「親なきあとの生活の不安」へと直接結びついてしまいます。でも、考えてみてください。ほとんどの親が後期高齢者になり、皆何かしらの不調を抱えていて、元気で問題の無い人なんて、周りを見回してもあまりいません。集いの会では、こんなことがあった、あんなこともあって大変だった、と皆に話すことで、家で一人で悩んでいたことも笑い飛ばすことができました。
集いの会は、少人数で何でも話せる場です。どうぞ、一度覗いてみてください。
(S.T)
4月19日(土)精神障がい者の地域移行について
~病院のケースワーカーの役割~
桜ヶ丘記念病院地域連携室 主任中原さとみ氏・金澤幸輔氏・高村由紀氏
参加者18人 (会員14人)
サンクラブ多摩では、会員家族の多くが外来または入院で桜ヶ丘記念病院にお世話になっています。そのため、当日はかなり暑く冷房も無い環境でしたが、いつもより多くの方が参加者されていました。
〈桜ヶ丘記念病院の概要〉
- 診察規模 ・病床数447床 病棟数8病棟(5月でもう1病棟閉じる) (精神科救急医療、アルコール、認知症、地域移行、療養型医療)
- 入院759件、退院778件(2023年度)、一日平均外来患者 約151名(2023年度)
- 職員数 312人(2024年8月現在)➡精神保健福祉士 14人(2025年4月から16人)
〈医療相談室〉
- 精神障がい者や精神疾患から生活に悩みを抱えている人の相談
- 外来や入院の医療費、退院後の生活、経済的な事、就労などの相談
〈多摩市福祉事務所との連携〉
- 生活保護受給者で精神疾患が疑われる人の自宅へ、担当ケースワーカーと同行訪問。名称は「健康管理支援員」 *最近20代が増えている、受診へ繋げる、手帳や年金などの説明
- 処遇困難ケースへの対応について助言等
〈地域連携室〉
- 精神保健福祉士と介護員が在室し、在宅支援(訪問看護指導・就労支援IPS) ➡ *IPS=Individual Placement and Support 個別就労支援プログラム
- 相談支援事業・居宅介護事業の管理・運営
- 東京都保健医療計画における南多摩医療圏域(多摩・稲城・日野地区)の管理運営。
- 「精神科医療地域連携事業」基幹病院として地域連携会議等を主催し、本事業を軸に地域、近隣の医療機関、関係機関と連携体制を構築
- 講演会開催、ボランティアの受け入れ等の相談
<主な質疑応答>
ホワイトボードに画像を写しての説明のあと、出席者から様々な質問がありました。
問:今までのグループホームが合わないので相談室で紹介してもらえますか?
答:ショートステイを利用してみるのが良いでしょう。市外の方でも障害者福祉法でショートステイを使えます。
問:短い時間の働き方ならできるのですが、そういう紹介はありますか?
答:紹介はしていませんが、一緒に探します。週一日、半日だけ働いている人もいます。
問:1日1時間の仕事が携帯に出てきますが、そういうのはどうですか?
答:そういう働き方は、忙しい職場が募集するので、教える暇が無いので、障害者では難しいと思います。
このほか、いろいろな家庭の事情の話が出ましたが、心配事がある人は一度相談室を訪ねてみてはいかがですか。
当日配布された詳しい資料があります。5月24日の総会の受付でお申し出いただくと、お渡しできます。 (S.T)
以降は2024年度の活動報告です
3月の活動
3月11日(火)集いの会
出席者3人(うち会員3人)
まだ会員登録していない方も参加して、それぞれのお子さんの小さい頃から今までの様子などの話が出ました。先月の交流会で、お子さんの復調を喜んで話された方は、また気になることが出てきたようで、「順調に回復する」ということが難しいのが精神疾患の特徴なのだと改めて思いました。
話し合いの途中で館内放送が入り、3.11東北の大震災と津波で亡くなった方の冥福を祈る黙とうを捧げ、銘々がその当時どこでどうしていたか、という話題に移り、あの時を思い出して語り合いました。
(S. T)
3月22日(火)簡単おやつ作りで交流
出席者11人(うち会員9人)
サンクラブでは、コロナ禍以降、調理や会食の企画は、社会環境の変化に対応して自粛してきました。以前は新年会では「草むら」の手作りのお弁当、総会後の懇親会では「れすと」のケーキ、公園での会員と家族でのバーベキューや、いろいろ楽しい交流を実施していたそうです。そこで、久々に復活しようということで、簡単おやつづくり「ライスペーパーを使ったピザづくり」を実施することになりました。過去は当事者の子どもの参加も多かったようですが、今回はPR期間も短く会員の認知度が充分とはいえず、役員や当事者も含め11人の参加でした。
ピザの土台は、さっと水にくぐらせたライスペーパーを3枚重ねて使います。和風は、そこにマヨネーズとじゃこを混ぜてベースにし、万能ねぎを散らしたピザ。イタリアンは、トマトソースをベースにソーセージ、玉ねぎ、ピーマン、コーンを敷き詰めて、いずれも最後はチーズをのせます。ライスペーパーは、コツさえつかめば簡単に活用でき、パリパリと軽い食感が魅力のヘルシーな食材です。
4班に分かれ、みんなで食材を切り、ライスペーパーをさっと水にくぐらせ、食材トッピングと、てきぱきと段取りよく進行! ベテラン主婦の経験があちこちで発揮されていました。当事者の参加がもう少し多ければ、家族とは別の人から生活の知恵を学ぶ機会にもなりえる可能性も感じました。おしゃべりしながら、ホットプレートを囲み、みんな焼けるのを心待ちにしていました。調理室では、簡単、おいしい、お酒のつまみにもいいなどの声が上がっていました。
終了後に参加者のお一人に感想を伺ったところ、「和気あいあいの雰囲気で、とっても楽しい会でした。特にじゃことネギのピザがおいしかったです。私が参加したのは、夫の食が細くて食べられるものが少ないので、新しい食物に興味があり行ってみました。ライスペーパーは生春巻きの皮を使い、簡単でおいしいけれど、焼くと少し固くなるので、今度は普通の春巻きの皮でも試してみようと思います。役員の方々にはお世話になりありがとうございました」
次の機会には、あなたも参加してみませんか。
(M.F)
3月30日(日)からきだの道ハイキング
出席者7人(うち会員5人)
10時唐木田駅集合。親子が2組、親だけが3人。参加者がちょっと少ないけれど、風もなく曇っていて暑過ぎず、歩くにはちょうど良い天気です。
唐木田駅のすぐ横の道から住宅に沿って歩き始めました。一戸建ての住宅地はどこもしゃれたお家にきれいな花や植木があって、とてもすてきです。
歩いて20分くらいで「お花見広場」に着きました。ソメイヨシノが何本もあって、まだ七分咲きですが、桜の淡いピンクとレンギョウの黄色、低木の黄緑がコントラスト鮮やかでとても美しかったです。ここのベンチで花を愛でながらのんびり一休み。
からきだの道は高低差があって、階段状の道が登ったり下ったりの繰り返しでちょっぴり疲れます。「榎戸公園」で1組の親子が疲れ過ぎないうちに、とリタイアしました。
その後もずっと上り下りの繰り返し。タケノコの皮がまだ付いている去年の春に出たと思われる太い竹が道にはみ出していたり、やぶ椿がたくさんあって、真っ赤な大きな花を落としていたり、所々でコブシの大木が花盛りで「わー、すごい!」「わー、きれい!」と歓声が上りました。
お弁当を食べる予定の「見晴らし広場」はまだまだ続く階段をいくつも超えて、12時15分にやっとのことで到着。日曜日だというのにすれ違った人はいても、休んでいる人は一人もいません。
多摩センターのビル群を眼下に眺めながら、それぞれが持ってきたお弁当を広げて「外で食べるご飯は気持ちよくて、おいしいわね~。」と大満足。その上、果物やお菓子をたくさん分け合って、お腹はパンパン!
「見晴らし広場」のすぐ下では桜並木が続き、朝に見た時よりずっと多くの花が開いていました。島田療育園の門の前で「からきだの道」は終わりです。5分位歩いて南部地域病院のバス停に着きました。ここで、多摩センターに帰る人と
唐木田に帰る人に分かれて解散しました。
(S.T)
2月の活動
2月10日(火)集いの会
出席者3人(うち会員3人)
このところしばらく顔を見せなかった会員が出席しました。具合でも悪くしているのでは、と、先月も出席者全員で心配していましたが、「家事だけで疲れてしまって、ここまで来る元気も無かった」とのこと。それぞれが、疲れているときの家事の手抜き方法などを出し合いました。
(S.T)
2月22日(土)豊田先生の交流会
出席者11名 (うち会員9名)
今年度3回目の豊田先生を囲んでの交流会です。先生は時間よりかなり早く会場にお着きになって開場を待たれていました。前回のお話では、「身辺がバタバタしている」とおっしゃっていたのが、やっと落ち着かれたのかと思いましたが、昨日新幹線に大事なパソコンを忘れて大失敗したことなどを話されました。まだまだお忙しい日々をお過ごしのようです。
今回豊田先生へお願いしたテーマは、「令和6年4月1日精神保健福祉法の改正点」です。昨年もお話いただいたテーマですが、もう一度あらましをお話いただきました。
・相談支援の対象が変わる
・精神障害者のほか精神に不調を抱える者も対象とする。
・医療保護入院の見直し
・今回の改正で入院期間を最大で6ヶ月とし、3ヵ月ごとに再検討する。
・「入院者訪問事業」の創設
・市長同意入院者を対象に指定の研修を修了した訪問支援員が、患者本人の希望により精神科病院を訪問し、本人の話をていねいに聞き必要な情報提供を行う。
・虐待防止に向けた取り組みの推進
・職員の虐待を発見したら、都道府県に通報することを義務付ける。
その後は順番に一人ずつ、子どもの事で気になっていることや、自分自身の気づきなどを出し合いました。今回は新しい方も二人みえて、現在の心配事などをたくさん話されました。
先生は、「親が元気で大丈夫だから何かがあった時、支援できる。『死にたい』と言う人は、ほんとうは死にたいのではなく生きたいのだけれど、『生きるのが辛い』からそう言っている。そこをわかってあげてください。」とまとめられました。
(S.T)
1月の活動
1月14日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
出席者4人(うち会員4人)
初めてこの会に参加なさった方が「滞在型グループホーム」について情報を探していました。会には「通過型グループホーム」を経て、「滞在型グループホーム」に入所している人や、「通過型グループホーム」の後、アパートでひとり暮らしをしている人もいるので、今月末の新年会で、そういう人たちからお話を聞いてみたら、と新年会にお誘いしました。
(S.T)
1月26日(火)新年会
出席者19名 (うち会員14名)
会場の都合で、変則的に日曜日の開催となりました。とても風の強い日でしたが、19名の方にご参加いただきました。
初めは恒例の歌の会です。植村先生のピアノ伴奏に合わせてみんなで歌を歌います。テーブルごとにリクエストした曲を、先生が伴奏してくださいます。
はじめのリクエストは「冬の夜」。♪いろり火は と~ろ と~ろ 外は冬吹雪
数十年振りに聞いた懐かしい歌でした。その後、「雪の降る街を」や「翼をください」などの曲をみんなで歌いました。初めは大きな声を出すのを躊躇していても、次第に声を出すのが気持ちよくなってきます。皆さんの歌声が重なるのもいいですね。
その後、会員ご家族の独唱タイム。お二人が「春一番」、「仰げば尊し」を歌って下さり、心をこめた温かな歌声、力強い素人離れした歌声に聴き惚れました。
生のピアノの伴奏は、カラオケとはまた違う、贅沢な響きです。特に「北の宿」や「津軽海峡冬景色」などの演歌は盛り上げ方がゴージャスで、思わずNHKのど自慢に出場したような気持ちで歌ってしまったのではないでしょうか。
植村先生は音楽療法士であり精神保健福祉士でもいらっしゃいます。小野路町の「ピアノカフェ ショパン」で歌の会の伴奏もされていらっしゃいますので、歌い足りない方はお出かけになってみてください。
次は会員Fさん考案の地名ビンゴです。16のマスの中に、多摩市の地名を入れていきます。落合、桜ヶ丘、永山など、多摩市には22の地名があるそうです。市外からいらした方も、わからない所を相談しながら埋めていきました。長年多摩市に住んでいる私でも、全部埋めるのはなかなか大変でした。
皆さんが全部埋めたところで、1人ずつ紙を引いていき、書かれた地名を読み上げます。それに合わせて丸をつけるのですが、5つ読んだところで早くもビンゴの方が出ました!1位の方には大きな100万円札!何かと思ったら、これはシート状の蒲鉾だそうです。そしてクオカードもプレゼントされました。他にも入浴剤やら、調理器具、便利グッズなどの様々な景品があり、皆さん選ぶのに苦労していました。
大声で歌って体も心も温まり、楽しい新年会となりました。最後に「れすと」のクッキーのお土産をもらって解散となりました。今回参加されなかった方も、来年はぜひ参加してみてくださいね。
(Y.U)
★★★会員お勧め映画「どうすればよかったか?」鑑賞記★★★
~会員紹介の映画を見て考えたこと~
前号の「サンクラブ多摩だより」に掲載された映画を見てきました。精神疾患の患者を家に閉じ込めていた「座敷牢」といわれる現実があったという歴史は知っていましたが、ノーマライゼーションが掲げられ、社会や家族のかたちが変化した今でも、別の形で厳然と家族の足元にあるという事を突きつけられた映画でした。
この「どうすればよかったか?」は、社会から隔たれた家の中で、発症した姉と両親との関わりを20年にわたりカメラを通して記録した映画です。家族との生活や対話を淡々とありのまま弟が撮影していた映像を、姉の死後、ドキュメンタリー作品としてまとめたもので、演出のないリアルな記録で構成された作品ゆえに、様々なことを私たちに提示してくれます。私にとって一番印象的であり、驚いたのは、高森先生がSSTで話される事と、映像を通して伝わってくることが、ぴったり重なっていることでした。
子どもが精神を病んだ時、病気に対する偏見や不確かな情報が、大きく親にのしかかり、不安は増すばかり。子どもは親の心を敏感に感じ取り、さらに症状は悪化していく。親密な家族であるがゆえに、親は事実を受け止めきれず、自分と子どもを同一視し、子どもが自分とは異なる他者であることに目をむけられずに、良かれと閉ざされた環境の中で先回りをし続けていく。
高森先生がよく紹介される「狂気は家族や仕事などの周りの環境がつくりだす」というイタリアのバザーリア先生の指摘が、姉と親とのリアルな生活映像にピッタリとあてはまるのです。親ゆえに「この子を何とかしたい」「我が子は統合失調症ではない」という強い思いで、当事者の意思抜きの独断的ともいえる決めつけが積み重なり、当事者である姉を追い詰めていきます。「我が子の今を認める」ことこそが、対話の第一歩! でも、目の前のありのままの我が子でなく、自分の思いが作り上げた我が子を前提に、必死に関わり続ける親の姿が描かれます。
対照的なのは、無力感を感じながらも、カメラを回すことで、親に現実を見てと訴え続ける弟。姉や両親に寄り添いながら対話を重ね続ける姿勢に、家族への愛を感じました。興奮した時に、姉は弟には暴力的にはならなかったということが、当事者にとって大切なものは何かを教えてくれます。世間的には大成功者である医師であり学者である両親が、目の前のありのままの娘を認められないまま、老いの影響もあって、姉を軟禁状態にして外に出さずに、家族ごと引きこもっていく様子がリアルに映し出されます。
両親の老化と病気によって家族生活が窮状に陥った結果、最初の異常で救急車を呼んだ時から25年を経て、初めて入院した姉。3か月入院し退院して見せた落ち着いて生気が漂っている表情の映像に、「よかった」いう感情と、「もっと早く治療につながっていれば、より豊かな人生が送れたのではないのか」という割り切れない思いが胸をよぎりました。
母親の死と父親の病気入院を経て、やがて父と娘の二人暮らしが始まります。精神疾患を抱えながらも、食事を作り、花を愛で、夜空の花火を見上げ、日常生活の小さなふれあいや楽しみを重ねていく姉の様子がスクリーンに登場し、その表情が柔らかくチャーミングで、「日々の生活の質」がいかに大事かを教えてくれます。その後、末期ガンにより62歳で亡くなってしまった姉。その姉への思い、変えることのできなかった家族関係への複雑な感情が滲む作品です。あらためて、SSTで学んだバザーリア先生の言葉の意味をかみしめました。
(F.M)

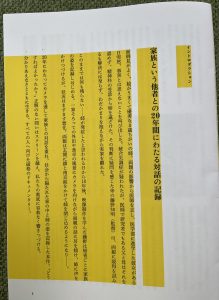
*映画「どうすればよかったか」は川崎市アートセンター(044-955-0107)のほか、イオンシネマシアタス調布(042-490-0039)でも上映終了になりましたが、また再開するという話も聞いていますので、直接上映館にお問合せください。
12月の活動
学習交流会は12月はお休みでした。
12月10日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
近々退院する予定で通院先を探していた方から、退院後の通院先が決まったとの報告がありました。入院するまで知らなかった病院なので、親子ともども不安で辛い思いをしたと話されました。
医療にもどこにも繋がっていないで引きこもっている人の家族の方が、皆から「一度『障害者地域活動支援センター のーま』に相談に行ってみたら?」と勧められて、相談に行く決心がついたようでした。
(S.T)
★★★会員からのおすすめ映画 情報提供★★★
「どうすればよかったか?」
ある家族の事例から統合失調症への対応を問う
ドキュメンタリー監督の藤野知明が、統合失調症の症状が現れた姉と、彼女を精神科の受診から遠ざけた両親の姿を20年にわたって自ら記録したドキュメンタリー。
面倒見がよく優秀な8歳上の姉。両親の影響から医師を目指して医学部に進学した彼女が、ある日突然、事実とは思えないことを叫びだした。統合失調症が疑われたが、医師で研究者でもある父と母は病気だと認めず、精神科の受診から彼女を遠ざける。その判断に疑問を感じた藤野監督は両親を説得するものの解決には至らず、わだかまりを抱えたまま実家を離れる。
姉の発症から18年後、映像制作を学んだ藤野監督は帰省するたびに家族の様子を記録するように。一家全員での外出や食卓の風景にカメラを向けながら両親と対話を重ね、姉に声をかけ続けるが、状況はさらに悪化。ついに両親は玄関に鎖と南京錠をかけて姉を閉じ込めるようになってしまう。
★上映館 川崎市アートセンター(新百合ヶ丘北口5分)
★上映開始時間 1月18(土)・19(日)・21(日)~24(金) 14:20
1月25(土)・26(日)・28(火)~31(金) 14:15
★上映時間 101分
★料金 一般1800円/大学・専門学校生1400円/
シニア・会員1100円/障がい者・付添(1名まで)1000円/
高校生以下800円
*チケットは上映日の3日前からオンライン申込か会場申込で。電話での受付はありません。
11月の活動
11月2日(土)第64回 高森先生の公開講演会
「みんなでやろう家族SST]
参加者 25名(うち会員12名)
◆当事者の結婚をめぐって
当事者の家族が抱えるお困りごとに、親身に寄り添い、全国を飛び回る高森先生ですが、過労から帯状疱疹を罹患されたそうです。そんな病み上がりとは思えない様子で、最初に、会場にいらっしゃった旧知の参加者の方を見つけて声をかけられ、結婚願望が強かったという当事者としての経験を引き出されました。以前は症状も重く入院を何回かしたけれど、現在は落ち着いており、2錠の薬を飲みながら、前向きに2年半の結婚生活を送っているという状況に、先生が当事者としての前向きな生き方と回復を喜ばれて、結婚に焦点を当てた話で始まりました。
結婚は健常者も含めストレスの第7位ということで、生活の違う人間同士の暮らしには、忍耐力と受容力が必要になってくることや、病気の子どもの事を中心にまわっていた親の方が、子どもの結婚による変化をうまく受け入れられず、子どもが騙されているのではないかと心配し過ぎる等の反応が起こることも、他の事例も交えて話されました。また、結婚や就職で、相手に病気の事を隠すか隠さないかについては、周囲の環境によりそれぞれ違ってくることなどにも言及されました。
「結婚してよかったことは?」という先生の問いに、「家から出られた事。最初は親がなかなか理解してくれなかったけれど、当事者の立場に理解がある優しい主治医の協力を得て、親を説得してもらい乗り越えた」と、明るく話してくれました。
自分のやりたい事を大事にしてきた積み重ねが、現在の彼女を作っている事を感じました。
◆当事者の心はヒリヒリ状態
20数年前に、高森先生が聴講された北山修氏(元フォーククルセダーズの音楽家で、精神科医と臨床心理学者でもある大学教授)の講演会では、全ての感覚に敏感な精神疾患の当事者の状況を理解する必要があることをわかりやすく話してくれたそうです(その講演内容概要は、「サンクラブ多摩だより2024年5月号」2~3ページ、または「サンクラブ多摩のHPの活動報告4月分」を参照)。それを踏まえて、先生は、次のように話されました。
この病気の人は、ドーパミンという神経伝達物質がたくさん出ているので、脳が人一倍敏感で、音や情報をたくさん受け取り、すべてにおいて、情報を先読みや深読みをしてしまいます。親が普通の会話と思っていても、当事者は「次の次」を読み取る。生まれつき、心を守るバリア層に欠損している部分があり、刺激にさらされると、ヒリヒリ状態。外部からのマイナスの刺激には、心の層が厚くなって刺激を遮断し、プラスの刺激には、その層が薄くなり心が開かれる状況です。東大のある先生は、「当事者のストレスとは、一番前の列で、素っ裸でみんなに見られている感覚」と例えているそうです。
一般の方は病気のメカニズムを知らないから、生まれつきの敏感さを理解しないで、「何をやるかわからない、狂人、危険人物」と位置付けてしまう。そんな中では、当事者は、耳に入る何気ない言葉に引っかかる。人の噂、人が自分をどう思っているかということが気になる。イタリアのバザーリア先生が「狂気は周囲の環境がつくる」と言っているのは、こういう事です。当事者が「自分を好きになる」「自分が一番知っている」「自分に自信を持とう」と思える環境が、何よりも大切です。
親は当事者に何が一番ストレスか、聞いてください。妄想や幻聴が出た時には、環境からストレスの種を取り除くことが大事。「自分の取扱説明書を書いてみて! お父さんも、お母さんも協力するよ」と、どういう言葉がストレスになったのか、本人から教えてもらうことが大事。大体の当事者は繊細、傷つきやすいと取扱説明書に書くが、それだけにとどまらずに、「どういう言葉が傷つくか」までを書いてもらい、それを言わないようにすることが、環境を整えるということにつながる。
「周囲に知られたら大変」という思いが親を苦しめる。親が偏見から解き放たれ、偏見のない社会を作ることが、味方を増やし、当事者の活動範囲が広がる。敵が増えれば、当事者は閉じこもる。敏感だからこそ、当事者の個性とそれが生かされると変わるということを忘れないでほしい。
◆家族ができる唯一の治療は当事者の話を聴くこと
精神科医の宮内勝先生は、「家族ができる唯一の治療法が、当事者の話を聴くこと」といっているそうです。私たちは、フィルター越しに話を聞いてしまう。フィルターとは自分の思い込み。そのフィルターを自分から取ることがカウンセリングです。フィルター越しに会話を聞くから誤解が生じる。
例えば、子どもからの「お母さん、暗くなったね」という子どもの言葉に、この子は私にばかり頼る依存型だと受け止め、「電気ぐらい自分でつけてよ」と返してしまう。また、近所から見はられていると言う息子が、紙をひらひらさせて家から出てきたところで、母親が有無を言わさず「早く家に入って」と言ってしまったり、父親が早く結論を出してめんどうにならないように切り上げたいという思いから「薬飲んで寝ろ」と言ってしまったり。
当事者は状況変化に弱いので、家族が当事者の病気の特性を理解していないと、かえって余計な刺激を与えてパニックを生じさせてしまう。そこで、まず相手の言葉を同じように繰り返してあげる方がいい。家族が変われば子どもが変わる! 良かれと思ってボコボコ言ってしまう親は、当事者からすれば自分の脳に合わないので受け入れられない。ぜひ、相手と同じ言葉での反復確認をやってみてください。
平和な関係のためには、時間をかけてくり返す。否定しない。説教もしない。心の中で苦しんでいること、困っていることを親がちゃんと聞いてくれると、不安や苦しみは半分に減り、混乱を起こさない。落ち着いたら、親がお願いの言葉で暴力を行使しないように語りかけること。
心の医師と言われ多くの精神科医に尊敬されている中井久夫先生は、患者の話をとことん聞いたそうです。小さな誤解が患者に少しでもあると、暴力的に抑えようとした場合、大変な事態になってしまうので、怒りの種を自分に話してほしいと患者と真摯に向き合い、そうして話しているうちに冷静になるということでした。絶対に相手に暴力で返してはダメ。暴力をふるってしまった息子を、親二人が実力行使で抑えつける事態になった事例では、それ以降、息子がボーと何もしない人間になってしまったそうです。
中井先生に習い、興奮して暴れそうになったら、家族で協力し、背後からわきの下を押さえる拘束術の「羽交い絞め」をして動けないようにし、耳元で「落ち着いて」と繰り返しささやき、周りの家族もみんなで「落ち着いて」と一緒に唱える。一人で対応する場合は逃げてください。そして、電話で「あなたが怖いからお母さんは逃げたのだよ。もうしないと約束してくれたら戻るよ」と伝えること。
◆親は安心を与える係
健康な心の条件は ①不安のコントロール ②怒りのコントロール ③状況変化に対処できる ④どれだけ他人に気配りができるか の4つ。これを踏まえ、家族は安心を与える役割を担ってほしい。子どもが不調で苦しんでいれば、「それ妄想だよ」と言うのではなく、「あなたの味方だからね。守ってあげる」と言ってください。4つの条件を理解し、親の愛と対応で、当事者の心を育てていってほしい。
◆お困りごと相談
今回の相談は次の2件でした。①息子の選択したトイレの壁紙に変えた事で、夫と息子の板挟みに悩む相談 ②双極性障害の娘に対する対応相談
最初の相談では、夫が抱えている当事者へのフィルターのもたらす影響の指摘があり、助言の後で、先生のリードでこの場合の夫へのSST対応をロールプレイしてもらい、みんなで学びました。
また、次の相談では、お姉さんのお世話係のなってしまっている健常者の妹さんへの心配も伴っており、啓発型の娘さんへの対応がとても難しく、心配が尽きないとのことでした。そのため、同調する言葉にもいろいろと工夫が必要で、先生から言葉がけの具体的な助言がありました。生活の中で、ほめる事を会話の中に入れる、ワンパターンでない共感の言葉が大事、背中をさする等のスキンシップを入れてみるなど、SSTの手法を活かした多様なアプローチも紹介されました。
(M.F)
11月16日(土)西晃先生 「統合失調症との付き合い方」
~発症から回復まで~
参加者 41名(うち会員23名)
現在、桜ケ丘記念病院に勤務され、週に1回は南多摩病院総合内科外来での内科診療、月に1日~2日は、往診クリニックでヘルプ診療をされているという西晃先生は、医師8年目、精神科医6年目の若手医師です。穏やかな口調と専門的な事項をわかりやすくまとめてくださった資料を使い、自己紹介から始まった講演会は、会員外の一般参加者が数多く参加されて満席。皆さん、熱心に耳を傾け、質問も多数寄せられ、閉会後には番外編で会場の部屋外で、先生に対応いただきました。いかに家族や当事者が、統合失調症に関する医師からの適切な情報を欲しているか、その気持ちが会場にあふれた講演会でした。
◆「精神疾患」「精神科」とは
精神疾患とは、脳の機能的異常によって症状が出現する心の病気の総称です。疾患の場合は、心臓は「循環器内科」、肺は「呼吸器内科」、消化器ならば「消化器内科」というように、脳の機能異常を扱うのが精神科です。
では、脳神経内科、心療内科との違いは何かというと、脳の機能異常が原因なのは同じですが、「出現する病状に違いがある」ということです。脳神経内科の場合は、パーキンソン病のように身体の動きに症状が出現する病気、心療内科は、過敏性腸症候群のように内臓の働きや身体症状が出現する病気、精神科は、幻覚や妄想、気分障害が出現する病気が対象になります。
統合失調症は、早期に治療につなぐ事が求められますが、親は焦って事態を見失ったり見当違いな対応に陥りがちです。このような基礎的な違いを正しく認識したうえでの判断や行動が大事な事が伝わってきました。精神科にかかるというと、家族にとっても当事者にとってハードルが高くなってしまうし、病識を正しく持つことが難しい面もありますが、この前提を踏まえ、正確な情報を得て客観的に事実を捉え、当事者に寄り添って臨む必要があるのだと感じました。
会場からの質問への回答コーナーの中で、先生が「病識が無い当事者に対しては、病名を明らかにしたり、病識を持つように強いるのでなく、当人がその病気によって困っている事を共有し寄り添って、その困りごとの解決のために、薬や治療に取り組んでもらうように働きかけをしている」旨の話をされました。病気への正しい理解が、何を目指しているのかという問題意識にそった的確な対応につながる事を、私たち家族も心がけておく必要を感じました。
続いて、精神疾患は不明瞭な部分が多い一方で、世間の認知度が上がっていることを具体的に紹介されました。統合失調症の発生率は1%前後であるが、気分障害は右肩上がりで、コロナ禍の影響等の社会背景が関与していること。発達障害は増加傾向(10年でADHD(*①)は6倍、LDは5倍、ASD(*②)は3倍)であり、晩婚化や高齢出産、障害に関する認知度の上昇などの影響が要因として考えられること。父親が35歳以上で子どもが生まれた場合の発達障害の発生率は高い傾向もあるそうです。
*①注意力欠如多動症:「不注意(集中力が無い)」と、「多動性・衝動性」の2つの特性を中心とした発達障害
*②自閉症スペクトラム症:「対人交流とコミュニケーションの質が偏っていること」と、「著しく興味が限定すること、パターン的な行動がある」の2つの特徴によって形づけられる症状を示す障害
なお、代表的な精神疾患と有病率についても紹介されました。気分障害では、うつ病が20歳~30歳代と中高年で多く、生涯有病率(一生のうちに一度はその病気にかかる人の割合)は100人のうち15人(15%)。双極性障害が10~20歳代に多く、生涯有病率は2%。それに対して統合失調症の場合は10~30歳代が多く、生涯有病率は1%。認知症の場合は、65歳以上の方の7人に1人で、2025年には5人に1人になるともいわれています。発達障害に場合は下記のとおりです。こういうデータを知ると、精神疾患と精神科は、現代の私たちの生活にとって、とても身近なテーマであり、より重要視されるべきだということについて、もっと社会的な理解が高まることを願わずにいられません。
・ADHD(注意力欠如多動症) 生涯有病率5%
・AL(学習障害) 生涯有病率5~15%(学齢期)
・ASD(自閉症スペクトラム症) 生涯有病率1.7%
◆統合失調症とは
お話の展開は、統合失調症に関する歴史的話題に及びました。統合失調症の様々な定義では、心や考えがまとまりにくくなるという共通点が見られます。それをシュナイダーは、「自我意識の障害と妄想知覚が中核」として捉えたそうです。自我意識の障害とは、体験が自分を離れる、自他との境界が曖昧になるということ。妄想知覚とは、外界の知覚したものに誤った意味付けをすることで、いわゆる妄想・幻覚と言われるものを指します。
1899年に早期痴呆として定義したドイツのクレペリンは、道徳療法として、患者を教会に住まわせ読書や作業等の日課を与えたそうですが、それが現在のデイケアと共通点があること。紀元前5世紀や中世ヨーロッパの歴史的記述の中にも統合失調症をうかがわせるものがあり、薬物治療以前には、自我を破壊するようなリスクが高く人権上問題がある治療もなされていたことが紹介され、1950年以降の抗精神病薬の開発や診断基準の改訂の歴史にも話が及びました。
しかし、いまだに統合失調症を診断するための客観的検査は存在していないそうです。そのため、症状や病歴、生活歴、既往症を聴き取る問診で診断を行うことになり、疫学的には、思春期から青年期(10代後半から30代前半)の発症が多く、発症率は1%で、30年から40年間数字が変わっていないことが謎であること。地域差や男女差はほとんどないが、男性でやや多いという報告も紹介されました。
◆遺伝要因と環境要因が関係する「多因子疾患」
統合失調症の原因は未だにわかっていないということで、「遺伝要因(受精卵ができた時点で決定している因子)」と「環境要因(受精卵ができた後で影響を受ける因子)」の両方が関与している「多因子疾患」と呼ばれるものに該当し、患者さんごとに発症の原因が異なる可能性があるとのことでした。
遺伝情報が同一である一卵性双生児の発症率は50%、両親や親せきが健常で子が発症する孤発症は少なくはない状況で、先天的な因子だけでは説明がつかないそうです。環境要因では小児期の逆境や大麻やコカイン等の薬物使用は発症リスクを高めることなどが分かっているそうです。
環境要因と遺伝要因の関係の例え話です。コップに注がれる水が環境因子で、水を受け止めるコップが遺伝因子と例えると、注がれる水の量とコップの大きさは、各人それぞれに違っていて、双方のバランスがくずれると、水はコップからあふれ(発症)してしまいます。注がれる水量が同じでも、コップが小さければ水は溢れ(発症)、逆にコップが同じ大きさでも、水量が多ければ水は溢れる(発症)。そういったバランスが発症に関係しているという解説でした。
◆統合失調症の病態・治療・経過
脳内の神経伝達物質ドパミン、グルタミン酸が関与していて、そのバランスがくずれ、陽性症状(妄想、幻覚、思考障害)、陰性症状(感情鈍麻、思考に貧困、自閉)、認知機能障害(記憶力低下、注意・集中力低下・判断力の低下)をもたらすというのが、統合失調症の病態です。その前兆期から急性期、消耗期(休息期)、回復期への各ステージに沿って、それぞれの病態や治療内容についてお話いただきました。前兆期と急性期は、睡眠・休息・安心感が大事で、過労・睡眠不足に要注意! 消耗期には楽しみながらのリハビリや体力づくりが大事で、無理は禁物。数か月単位の休息、規則正しい就寝時間であせらず無理せずに! 回復期から安定期も、精神状態の安定と周囲への関心や自発性が戻ってくるよう、引き続き楽しみながらのリハビリや体力づくりに取り組む!
一方、回復期から安定期では、「薬をいつまで続ければいいのか」という課題が生まれてくる。回復した状態が続いている(寛解)を維持するためには、抗精神薬の継続は必須です。現状のエビデンスでは、可能な限り継続した方がいい。2年以上安定していれば少し量を減らすことはできる。服薬をやめると攻撃性があがるので、医師としてOKするのは難しい。症状の安定には、薬物治療の継続が必要。他の慢性病のように、「長くつきあう」「回復を目指す」姿勢でいきましょう。
長く服薬を続けるためには、飲みやすさや扱いやすさは重要であり、今は、薬も改善され、張り薬や1か月に1回の注射で効果が維持できる持効性注射剤等、様々なものも出てきているので、主治医と相談をすること。
◆統合失調症とどう関わっていくか
【抗精神薬の代表的副作用を知っておこう】
長く服薬を継続するためには、副作用の出現には注意が必要なので、代表的な副作用を知っておくことが大事です。副作用がある場合は、減薬や変薬を主治医と相談していきます。副作用とされている「血糖値上昇」「体重増加」「アカシジア(そわそわ・じっとできない)」「高プロラクチン血症」「抗コリン作用」が、服薬している抗精神薬と関連するかを把握しておき、十分注意を払う必要があります。特に重症度の高い副作用として注意が必要なのは、遅発性ジスキネジア(身体の一部が勝手に動いてしまう)と横紋筋融解症(筋細胞が融解、壊死)の2つです。
【それぞれの当事者の困りごとへの関わり】
同じ病気かと思うほど、統合失調症患者の状態や経過は個人差が大きく、重症度、どの症状で困っているかも異なる。また、精神科患者の循環器や悪性腫瘍、生活習慣病などの身体疾患の死亡リスクも上昇傾向にあり、内科医師と精神科医の連携も必要になってきている。
そして、当事者の情緒的な安定には、家族環境面の調整が不可欠であり、感情表出が高い家族の場合、情緒的緊張レベルが高いと症状が再燃しやすくなる。家族の病気の知識がないと当事者はストレスを感じるので、本人のためにも、家族は病気の知識をもっておいてほしい。他の家族の理解を得られずに一人で問題を抱え込んでしまうことも禁物である。そのような場合は、訪問看護等との連携も考える必要がある。
統合失調症は「こころや考えがまとまりにくくなってしまう病気」と言われていて、本人も何をいいたいか、何を考えているのかわからなくなっていることがあるので、「病気である」「病気でない」に終始しないで、当事者や家族が何に困っているか、何を目指したいのか「こころ」の動きにも着目しながら関わっていけるようになるといいなという先生の思いが伝わってきました。
その後、先生が関わった患者さんの次の3事例について、前兆期、急性期、回復期(安定化期)、安定期の状態の変化を中心にお話いただきました。
- うつ病と診断されていた20代の女性
- ひょんな声掛けから外出が増えた50代男性
③ 剤形(飲み込んで服用する薬)の変更によって再入院しなくなった60代女性
最後のまとめとしての先生からのメッセージです。「統合失調症は精神科医でさえ、まだわからないことの多い病気で、家族が自身を責める必要は全くなく、回復に向けてどうしていけばよいかを相談していくことが重要なこと。家族だけで抱え込むのは、当事者にとってもメリットではなく、困ったら躊躇しないで主治医に相談してみること。病気に関する正しい知識を身につけ、家族も趣味やリフレッシュをする時間を作ってください」
このあと会場からの具体的な質問(病識のない当事者への対応、投薬に関する疑問点、セカンドオピニオンについての見解等)に対し、それぞれに丁寧かつ簡潔に答えていただきました。中には若き医師への期待と激励のメッセージも飛び出し、先生からは患者のキャッチアップにつなげるために内科医と精神科医を兼務していることや、精神科が総合内科の一部と捉えた方向性についての見解が示されました。講演会終了後は、先生と直接話したいという方が並んでいました。
講師の率直さ、当事者に寄り添い、当事者や家族の視点を大切にする真摯な姿勢に感銘を受けた講演会でした。
(M.F)
11月12日(火)集いの会
出席者5人(うち会員5人)
今回も、発症からまもなくの頃の暴力やさまざまな困った症状にそれぞれの家庭でどのように対応してきたかに話が及びました。
最近少し落ち着いてきたと話す方が、毎年お誕生日に「あなたはわが家の大事な宝物です。」と手紙に書いて渡すと話され、一同から尊敬の賞賛を浴びました。
(S.T)
10月の活動
10月1日(火)集いの会
出席者5人(うち会員5人)
今年になって入会された方が来てくださって、話題が子供時代のことまで遡りました。いじめや学校の対応、スクールカウンセラーや保健室登校など不登校だった時代のさまざまな出来事に話が及び、みんな辛い思いを経験してきていることがわかりました。
これからどうしていくか、とりあえず現状維持で先の展望が開けないのは同じです。親亡き後をどうするか、毎回この会の答の出ない課題です。
(S.T)
10月26日(土)学習交流会 ~豊田秀雄先生を囲んで~
参加者 8名(うち会員7名)
6月に続いて今年度2回目の豊田先生の交流会です。先生は7月に相談支援事業所を開設したばかりなのでまだバタバタしている、とのことでした。また、私生活でも入院中のお母さまがかなり重篤になられたので、そのことでも毎日の暮らしにいろいろ変化があるということも話されました。
今回サンクラブ多摩から豊田先生へは、「買い物依存やゲーム依存について知りたい」とお願いしていました。
ゲーム依存の話から始まり、ゲームをすることで脳内にドーパミンが大量に分泌されて心地よさ(快楽)や喜び、高揚感・興奮に繋がると言った話とともに、ドーパミンは統合失調症の原因物質とも言われている、という話もありました。
ゲーム依存(ゲーム障害)については2022年にWHOの診断基準(I C D11)に入ったとのことです。
買い物依存の話の中では、「買って使うことに喜びを感じるのでなく、買い物している過程に陶酔している」といった話がありました。
依存全般の話としてアルコールや薬物の入った物質への依存、今回のゲームや買い物・それとギャンブルなどのプロセス(過程)の依存という話があり、後半の参加者の話を受けて、人への依存(共依存)についても少しだけ触れてくださいました。「その人がその時々で本来行うべきことが依存の原因となる物質・行動によりできなくなっている状態」とも。それはコントロール障害ということ。どの依存にもこのコントロール障害は共通するところです。
この他アルコール依存の話の中では、身体依存と精神依存、飲酒中心の生活、耐性や離脱症状、飲んだお酒が体から抜けるまでの時間(分解時間)といった話がありました。
その後、参加者全員が依存症に関わらず、一言ずつ話しました。アルコールには問題無くても、タバコやコーヒーの量が多くて心配だという家族もいました。それに対して先生は、コーヒーやタバコは飲んでいる最中には幻聴から逃れられるという人がいる、ということも話してくださいました。アルコールに関しては、深夜にアルコールを飲んでいる時間が長いのでとても心配と深刻に話される家族もいて、アルコール依存症の大変さを実感しました。
また、長年親戚のひとり暮らしの当事者から電話で話を聴いている人からは昼間仲間に言われた嫌な事を「他人(ひと)が何と言っても自分は自分だ、と思った」と聴いてとても嬉しかったので褒めたという話に、先生から回復にはとても長い期間が必要で、親はもっと早く回復して欲しい気持ちが強すぎる、とコメントがありました。
終わってから、「今日は先生が一人一人の話にコメントをくださったので、とても良かった。」という感想が聞かれました。
(S.T)
9月の活動
9月10日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
一人っ子で、いつも親亡き後のことをいろいろ調べている方は、同じく一人っ子で後見人を付けている人に、どのタイミングで付けたらよいかを聞き、親が入院するなど、現状が変わった時がタイミングと言う話に、ちょっと安心したようでした。
しばらくぶりに参加した方がいました。他の人たちはその方の事をお身体の具合でも悪くしているのでは、と心配していましたが、そうではなかったと聞き、ほっと一安心。その方が「だんだん年を取って家事が負担になってきている」と話されたので、皆で自分は家事のどこを手抜きしているかで盛り上がりました。
(S.T)
9月28日(土)学習交流会
テーマ:「あんどの相談事業」と「兄弟姉妹との関係」
~地域活動支援センター「あんど」相談員を囲んで~
家族にとって兄弟姉妹、または親との関係はとても大きな問題です。このテーマを話し合うときに家族同士だけでなく専門家の助言、アドバイスは必要ということで、「あんど」からお二人にスタッフにおいでいただきました。
「あんど」とは
多摩市に住む障がい者が自立した日常生活を営むことができるよう、創作的な活動・生産的な活動の機会を提供し、社会との交流の促進をはかることを目的としています。総合福祉センターの中にある多摩市社会福祉協議会が市から委託を受けて事業を行っています。
〈相談支援事業〉3階窓口
★総合相談(一般相談)
18歳から介護保険適用前までと年齢層が厚い相談を私たちの他に4人で受けています。日常生活や治療、福祉サービス、就労までの「何でも相談」です。複数回の場合も含めて8月は46件の相談がありました。健康センターの中にある「のーま」でも同じ内容で相談を受けています。
障がい者手帳だけでなく、自立支援医療証でも相談を受けられます。
★指定特定相談(計画相談)
初めて障害福祉サービスを利用する時は介護保険のケアプランと同じく、サービス等利用計画の作成が必要となりますので、その相談を受けています。
あんどの相談員さんから説明をして頂いた後で、一人が自分の家の困りごとを出し、それについて皆で話し合いました。兄弟姉妹との関係の具体的なお困りごとや、当事者の金銭管理の悩みについての話題でした。
どのケースも深刻で、質問はいろいろ出ましたが、難しくて、困っている家庭に対して納得のいく解決策などは見い出せませんでした。
(S.T)
8月の活動
8月13日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
最近入会された方が一番に見えました。学習交流会では大勢なのであまり自分の事ばかり言うわけにもいかないので、参加してみたとのこと。小さいときのことから発症の経過で辛かったことや現在の困りごとが少し前に進んだことなどを話して少し気持ちが楽になったと言ってくれました。
成年後見制度についていろいろ調べている方は、先月話題に出た「多摩南部成年後見人センター」に電話したけれど、逆に住まいの「社会福祉協議会」に相談するように言われて、これでは堂々巡りだ、とがっかりした表情で報告してくれました。
(S.T)
動画で学ぼう! 会員からの公開講座の情報提供
「ひきこもりを理解し、誰もが生きやすい社会を考える」 動画のご紹介
6月にオンラインで開催された、「第9回 精神障がい者と家族のための市民公開講座」がWebサイトで公開されています。いつでも、スマホやパソコンで見ることができます。専門家の先生方の支援の取り組みについてのお話や、当事者や家族の方のお話も視聴できます。Q&Aセッションでは、講演者の皆さんが丁寧に回答しています。
<市民公開講座の内容>
「ひきこもり」とは、状態をあらわず言葉で、病気の名前ではありません。ただし、多くのケースで発達障害やうつ病・統合失調症などの精神疾患を罹思していると言われ、原因のひとつである場合があります。ひきこもり状態にある人は、全国で15歳から64歳までの年齢層に約146万人と推計されています。(内閣府「こども·若者の意識と生活に関する調査 令和4年度」)
性別・年代に関わらず、さまざまな理由でひきこもりになる可能性があります。当事者も家族も地域との関わりを絶ち、孤独・孤立の中で、なかなか支援に結びつかないことが課題となっています。
本市民公開講座では、「ひきこもりを理解し、誰もが生きやすい社会を考える」ために、それぞれ経験豊富な専門の先生から、また当事者やご家族の立場からご自身の体験についてもお話しいただきます。会の後半のパートでは、Q&Aセッション(質疑応答)の時間を設け、視聴登録して頂いた当事者やご家族などから事前にいただいた「ひきこもり」に関する質問について講演者の皆様からご回答いただきます。
<動画へのアクセスは>
大塚製薬の「すまいるナビゲーター」というサイトのに入ると、トップページの一番下の方にリンクがあります。過去に開催された、うつ病や双極性障害についての公開講座も見ることができます。次に、過去の開催した市民講座一覧をクリックすると、「動画で見る精神障がい者と家族のための市民公開講座」へ入ることができます。第9回講座に入ると、「動画視聴ページへ」の表示があるのでクリックします。
☞こころの健康情報局 すまいるナビゲーター (https://www.smilenavigator.jp)
☞精神障がい者と家族のための市民公開講座
https://www.smilenavigator.jp/information/event/shiminkokaikoza/koza9.html
☞第9回 精神障がい者と家族のための市民公開講座
「ひきこもりを理解し、誰もが生きやすい社会を考える」の中の「動画視聴ページへ」をクリックする。
(Y.U)
7月の活動
7月6日(土)第63回 高森先生のSST講演会
「みんなでやろう家族SST」
参加者 33名(うち会員 17名)
梅雨の晴れ間、猛暑にかかわらず、市域を超えて多数の参加がありました。開始直後、会場の隅にあった電子ピアノに目を止められた高森先生からの突然の提案で、参加者全員で「バイバイ ブロンディ」を合唱し、会が始まりました。
◆歌と手話で「I love you so」
「バイバイ ブロンディ」は、アメリカの新聞連載の4コマ漫画が、後にアニメ化された人気番組の主題歌です。歌の紹介をしながら高森先生が歌詞を板書。その後、歌詞を表現する手話を身振り手振りで参加者に伝授してから、先生のピアノ伴奏のリードで手話&合唱の楽しいプログラムが展開されました。思わぬ展開にみんなで驚きつつ、板書を見ながら歌を口ずさみ、手話で必死の表現。会場は、いつの間にか明るい雰囲気に包まれていました。
歌の後、歌詞の中の「I love you so」という部分について、先生が言及しました。ある家族会の講演会で、みんなでこの歌を歌ったが、さっそく家に持ち帰り、子どもと一緒に「I love you so」の歌と手話を実行した母親がいたそうです。その後に同じ家族会で、当事者も交えて同じプログラム実施した時に、先生は、屈託ない明るさで参加しているのが、その方のお子さんだとすぐわかったそうです。親子のコミュニケーションで、親のI love youが伝わっていると感じたそうです。
「この会場に皆さんが足を運んだのは、少しでもわが子を良い方向にもっていきたいという親の愛情があるから。家族会で学んだり経験したりした事を糧にして家に持ち帰り、家族にも上手に伝え、日々の生活を少しでもさわやかにしてほしい」というのが、先生からのメッセージでした。
ちなみに手話では、小指を立てて「I」の指文字・ 親指と人差し指を立てて「L」の指文字 ・親指と小指を立てて「Y」の指文字になり、3本の指をまとめて立てるので「I LOVE YOU」を表すサインになります。
◆まず親が「I love you」を伝えることが始まり
松江で150名の専門職参加者を前に、高森先生が講演をした際、医師と患者の診察という場面設定で、参加者全員でロールプレイをやった時のエピソードです。患者役に、医師に伝える事4点を設定し、注意点や会話を深める言葉の例を具体的に示しながら実践に入ったところ、頭のいい人はすぐに自分の意見を言ってしまい、相手の試行錯誤を許さない傾向や、医師は上から目線で話しがちなことなど、コミュニケーションの課題が浮かび上がったそうです。
次の事例は、大学卒業後、一人でロンドンに渡りカルチャーショックから発症した女性の話です。幻視で父親も認識できない状態で、羽田から病院に直接搬送され入院。合う薬が無く全然よくならずボロボロの状態。連日、面会に通う母親が、娘から「愛しているの?」と問われたときに、返事ができず、自分の中に無意識に「娘が家に不幸を持ち込んだ」という怒りと憎しみの気持ちがあることに気づいたそうです。
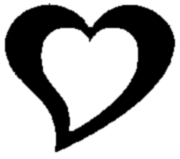 高森先生は、心はどうあれ、「I love you」と当事者に親が伝えることが大切であり、それにより親自身の心が変わってくることを説明されました。家で、「I love you so」の手話で働きかけをすることは、親がまず、自分が変わる行動をすることで、子どもを変わりやすくしてあげる行動療法ともいえるのです。
高森先生は、心はどうあれ、「I love you」と当事者に親が伝えることが大切であり、それにより親自身の心が変わってくることを説明されました。家で、「I love you so」の手話で働きかけをすることは、親がまず、自分が変わる行動をすることで、子どもを変わりやすくしてあげる行動療法ともいえるのです。
◆自分と未来は変えられる(親が変われば子が変わる)
コンボ(地域精神保健福祉機構)が発行するメンタルヘルスマガジン7月号「こころの元気」に、「親が変われば子も変わる」という高森先生の原稿が掲載されています。この掲載原稿をベースに、次のような説明がありました。
4月に講演に行った先々で、参加者に、自分が意識して変わったところについて書いてもらったところ、「ほめるようになった」「ありがとうと感謝する親になった」の回答が多く70%~80%を占め、一方、治療的効果がある「話を聞いてあげる」については、一番意味があるのにやっていない人が多かったとのこと。
「不安」「過労」「不眠」「孤立」の4つが揃うと、だれでも様々な症状が出てきます。不安は安定剤等で、不眠は睡眠剤で抑えられるし、過労は不安と不眠が少なくなると緩和される。しかし、孤立に合う薬はない。だから、家族は安心をあげる役割に徹してほしい。この病気は敏感だからストレスを受けやすく、人から愛されたい病気なので、大好きだということを親の言葉と行動、態度で伝えてほしい。
全家連の当事者へのアンケートでは、ストレスを誰から受けるかのトップは、家族でした。親は何とか病気を治してあげたいと思うが、親のレベルに引き上げようとすれば子どもは拒絶するので、親が子どものレベルに合わせて、子どもが変わりやすいよう、先に変わってあげるのです。親と会話をしたくない子どもの現在位置に合わせ、返事を求められない言葉で、声掛けだけする。安心して心を開いてきたら、次の段階。ほめる言葉や「ありがとう」の言葉での会話をしていく。子どもを引き上げるのでなく、寄り添ってください。当事者のアンケートでは、No1「もっと私の気持ちをわかってほしい」、No2「つべこべ指示しないで」No3「私を傷つける言動をしないで」でした。家族に変わってほしいという当事者の思いです。
相手の話をわかるために大切なポイントは、すぐ問題解決を図ろうとしないで、まず相手の気持ちをわかることを先にやること。Social Skill Training(SST)は、その実践です。アメリカでリバーマン先生が考案した社会生活を送るコミュニケーションのための3技能のトレーニングは、薬以外の力で、コミュニケーションの質の向上を図るもので、精神疾患の再発防止や生活の質の向上に良い影響があります。3技能とは、①受信機能 ②処理機能 ③送信機能を指します。
◆反復確認がキーポイント
先生の掲載原稿にそって、「相手の気持ちをわかるための大切なポイント」の解説がありました。中でも、最も重要として強調されたのが反復確認です。5段階のSSTのプロセス(①関心表明・②反復確認・話が具体的になるための質問・④共感の言葉・⑤自分の考え)の中で、②と③プロセスに十分時間をかけることが重要です。反復確認は、当事者が「自分が大事にされている」と実感できる。これがビタミン愛なのです。
相手の言ったことを相手と同じ言葉でくり返すので、敏感で色々な事を受け止めすぎて変化に弱い当事者の気持ちに変化を起こさない。病気で脳が急変を処理できないので、親のレベルに合わせようとしない。調子の悪い時ほど、相手の状況にあわせてあげることが必要。「口で寄り添いながら、親の目力で圧力をかけることのないよう、親は焦らない、頑張りすぎない、無理をしない! 『ア・ガ・ム』の気持ちで家族が話を聞くことが治療の始まり」という先生の言葉が心に刺さりました。
◆2つのゲームで反復確認と表情&態度で伝える実践体験
休憩後、高森先生からの提案で、SSTの技能を磨くために、①反復確認の練習と、②表情から感情を読み取る2つのゲームをみんなで実践しました。
最初のゲームは、リーダーが自ら考えたテーマにそって2つの単語(事柄や名称等)を発表し、会場の中から1名の方を指して、もう一つ(プラスワン)を付け加えてもらい、会話で反復しながら確認し、指名されて付け加えた方が次のリーダーになるゲームです。
次は、カードに書かれている状況設定等をリーダーとリーダーが選んだ人物1人だけで共有し、リーダーに選ばれた人物が、カードの内容にあわせた感情を表情で表し、それ以外の参加者が表情から感情を推察するというゲームです。
双方とも、SSTの3技能をフル稼働! 反復したつもりで、言葉を端折ってしまったり、ありがとうの言葉を添えるのを忘れたり、自分がリーダー(主役)になった時に、テーマが浮かばず慌てたり、表情を読み取るのが意外に難しかったり、そして、現実には表情ができない当事者もいるという事実もあったりと…。笑いの中で日常のコミュニケーションやリアクションを振り返り、見落としがちな事に気づく機会になりました。
「親が自由に笑えるような存在になった方がいい。笑いはエンドルフィンという幸福ホルモンを生む。うれしそうな表情を忘れないよう、楽しい感情をわき起こすことが大事」という先生の言葉を実感したひと時でした。
◆お困りごと相談
締め括りはいつも通りです。会場から寄せられた相談2件(お子さん関するもの・高齢の母親に関するもの)に関し、相談者と先生がやり取りをしながら、具体的な情報提供と助言で終了しました。 (M.F)
7月9日(火)集いの会
出席者3人(うち会員3人)
先月に引き続きご主人の体調がすぐれないことで心配している方は、もし病気の子どもと二人だけで残されてしまったら、と考えると経済的な不安やその他の不安が次から次へと浮かんできてとても辛いとおっしゃっていました。そこで、成年後見制度の相談先とか生活保護の条件や基準についての話も出ました。ご主人の体調が良くなれば不安も軽減するのでしょうが、誰でも一年一年、年を取るので前もっていろいろな制度を調べておくことは大切ですね。
集いの会は少人数で何でも話せる場です。どうぞ、一度覗いてみてください。 (S.T)
7月27日(土)学習交流会
「東京つくし会」とは?(つくし会家族会訪問)
~つくし会副会長の本田道子氏を迎えて~
参加者10名(うち会員9名)
ある会員から、毎月「サンクラブ多摩だより」に同封されている「つくしだより」を読んでいるが「つくし会」について詳しく知りたいという要望があり、以前に訪問していただいてから大分経っているので改めてお願いする形で今回の家族会訪問が決まりました。
〈自己紹介〉
本田さんは二人のお子さんが障害を持ち、上のお子さんはグループホームとアパートでのひとり暮らしを経て、現在は都営住宅に住まい、就労を続けています。下のお子さんもグループホームからアパートでのひとり暮らしをしていましたが、そのアパートの立ち退きに対して自分で家探しをするなど、現在ほぼ自立して暮らしています。ここに至るまで長期間のひきこもりや暴力など大変なこともたくさんありましたが、専門家の力を借りて夫婦で乗り越え、現在は子どもさんのことは何も心配していらっしゃらない、とのことでした。
本田さんは、現在渋谷区の精神障害者の家族会「渋谷太陽の会」の会長をなさっています。太陽の会では渋谷区に要望して、精神障害者にはタクシー券、区の福祉手当8,000円を支給されるようになったとのことです。
「太陽の会」も「サンクラブ」と同じように毎月例会をしていて、出席者は10人弱くらいですが、保健所の講堂を優先的に借りられるので、会場確保の心配はない、ということです。補助金は渋谷区の障害者団体連絡会から50,000円が講師料として、あと社協から50,000円があるそうです。
〈東京つくし会〉
東京都の家族会49団体が加盟していて、理事は9名で運営していて皆ボランティアで交通費だけが支給されています。つくし会は23区と多摩地区に分かれて活動しています。8月31日に多摩ブロック会があり、午前中は相談員養成講座で午後はブロック会議です。
7月から9月にかけて東京都に対して来年度の予算編成に向けての要望書を提出します。その内容は以下のとおりで、1と2は重点要望です。
1.早期発見・早期治療を促進し、治療中断・再入院を回避するため、アウトリーチ(訪問診療)拡充で精神科医療に繋げてください。
2.精神科医療の充実
3.精神科休日夜間救急診療については、次の措置をとってください。
(1)民間精神科病院群で構成される輪番制の担当地域を複数に分割してください。
(2)やむを得ず家族が患者の移送のため、民間の護送サービスを利用せざるを得なかった場合には、都において移送利用料金を補助してください。
4.思春期における精神疾患の早期発見のために以下の事を行ってください。
(1)中学生を対象にした精神疾患を理解する内容のパンフを毎年作成してください。
(2)児童・生徒の状況を身体・健康面、心理面の観点から捉え把握することなど教職員の支援力をつけるための研修の機会を増やしてください。
(3)障害者週間に、一般都民に精神疾患に対しての偏見をなくし、正しい理解を得るための講演会やYouTubeでの動画配信など工夫した取り組みを行ってください。
(4)都が配置している東京都公立学校のスクールカウンセラーを常勤化してください。
5.精神障がい者にも福祉手当を支給してください。
6.重度心身障害者医療助成制度(マル障)を2級手帳保持者も対象にしてください。
7.家族会活動への支援
(1)家族会の活動拠点である事務所は、本会の会員の会費によって賄われており、不安定な状況です。全国精神保健福祉連合会の関東ブロックに所属している6県では、すべて精神保健福祉センターのような公的施設を利用しています。都におかれましても施設貸与か賃借料の支援をお願いします。
(2)市区町村のアウトリーチにおいて家族会が育成した相談員を活用していただきたい。
また、都民ファースト・公明党・共産党・立憲民主党などの都議会各会派からのヒアリングも予定されています。
〈相談員として家族に伝えたいこと〉
都庁で福祉関係の相談員として電話相談と面談に従事していた関係で、つくし会でも電話相談をされており、時々面談もされているようです。
「相談では、まず相手を受け止めることが大事です。年をとると、思っていても動けなくなります。行動に移さなければ思っていても変わりません。相談だけでは変わらないのです。」という本田さんの最後の言葉が胸に響きました。(S.T)
6月の活動
6月11日(火)集いの会
出席者2名(うち会員2名)
いつまで待っても人数が増えず、最初から最後まで二人きりでした。話題は広がりませんが、その分、小さい頃のことから初めての入院とその後の通院、今に至る経過と先行きの心配事などをじっくり話すことができました。
集いの会は少人数で何でも話せる場です。どうぞ、一度覗いてみてください。
(S.T)
6月21日(金)東京つくし会評議員会
参加者1名
会場は調布市文化会館(たづくり)8階映像シアターでした。朝から雨が降り続く中、47の家族会が参加しました。
真壁会長の挨拶で始まりました。
昨年度は滝山病院事件に関係する様々な取り組みを行ってきました。特に大きかったのが都議会あてに「医療機関における精神障害者への虐待をなくし適正な医療へのアクセスを可能とする陳情」を提出し、全会一致で趣旨採択されました。そのことに自信をもって新年度に向けてやっていきたいと思います。
来賓の挨拶では、各政党の都議会議員、手をつなぐ育成会理事、みんなねっと事務局長から一人約1分30秒のスピーチがあり、行政からは東京都精神保健医療課長が出席しました。議員のお一人から「家族会は地域で精神障害者の方が暮らすうえで大きな役割を果たしておられます。家族会の方のみなさんの重要性をもっともっと東京都として応援すべきではないか」と言う心強い言葉がありました。
令和6年度東京都予算には、①精神科病院における虐待の通報窓口の設置、虐待防止研修の実施、②身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業、③区市町村長の同意による入院者への訪問支援事業が新規に盛り込まれました。このことは大きな成果に思うと言う報告でした。
東京つくし会の赤字財政解消のため、事務局員2名体制を1名に削減せざるをえなくなり厳しい状況です。賛助会員の拡大をしていきたいと思います。地域のクリニックや病院に頼んでいただきたいというお願いがありました。
提案された2023年度事業・活動報告及び2024年度事業・活動報告は全て承認されました。詳しい内容については7月以降の「つくし便り」に掲載されますので是非ご覧ください。
会の終了後、午後から講演会がありました。
テーマ: 精神障がい者が事件を起こしてしまったら
~被害者への損害賠償は家族が負担?~
講師: 弁護士 奥田 真帆 氏 (立川アジール法律事務所)
(K.F)
6月22日(土)豊田先生の交流会
出席者12名(会員11名)
前日梅雨に入ったばかりの土曜日でしたが、さいわいこの日は雨にも降られず、最近会員になった方が多く参加して少しでも多くの情報を得たいという気持ちが感じられました。
前回のお話では、先生は相談支援事業所を立ち上げる準備をしているということでしたが、数日前に事務所のある自治体から「やっと東京都から指定の認可が下りた」との連絡を受けたそうです。自治体によっていろいろと言うことが違うみたいで、かなりご苦労なさったようですが、いよいよ7月1日に『サポートハブ巣鴨』という名称で開設することになったということでした。
サンクラブ多摩から豊田先生への要望として、最近新しく入った方も多くなり、病気についてもっと知りたいので、例えば、「水中毒」や「アルコール依存症」を代表とする「依存症」などについて、お話していただけないかとメールでお願いしてありました。先生は、「僕は医者ではないから」と断わった上で、そのことについてのお話がありました。
〈水中毒〉
水を飲み過ぎることによって電解質(ナトリウム・カリウムなど)のバランスが崩れて、意識障害を起こすこと。死に至ることもある。
統合失調症の薬、うつ病の薬の副作用で喉が渇く → 水を飲む →電解質が薄まる → 腎臓・肝臓に負担がかかる(2~3ヵ月に一度は採血をして調べる必要がある)
〈アルコール依存〉
禁断症状の時に幻聴・幻覚が出ることがある。一般的にアルコールは薬の効果を高めたり、薄めたりする。向精神薬を飲んでいる人も同じ。タバコも同じで飲んでいる人は落ち着くと言う。ニコチンが向精神薬の代謝に影響を与えるという研究がある。
①グループ 酒を止めるのだから、タバコくらいしょうがない。
②グループ 酒を止めるなら、タバコも止めなければしょうがない。
という二つの考え方があるが、本人にとってメリットが無ければ止められない。家族がそれをやることは難しい。きちんと本人に説明してくれる人がいることが大切である。
その後、参加者全員が一言ずつ気になっていることなどを話しました。その中で、主治医との関係で悩んでいる方の話があり、それに対して先生から相性という話と参加者から主治医の立場への理解という発言もありました。個別相談は1件でした。
(S.T)
5月の活動
5月14日(火)集いの会
出席者4人(うち会員4人)
最初から後見制度に関する質問で始まりました。親亡き後の日々のお金の管理や持ち家の維持管理に対する不安から、どこに相談したら良いかという疑問でした。
それには、住所地の社会福祉協議会の権利擁護センターが窓口になっているので一度相談に行ってみてはどうか、ということでほんの少しホッとしたようです。多摩市ですと総合福祉センター7階にあります。
そのほか、自分の健康状態も良くないけれど、もし連れ合いが先にいなくなった場合は家計が立ち行かなくなるのでは、という心配も出ました。どうなったら生活保護が受けられるのかという疑問も出て、3月の学習会に出席した人が生活福祉課長から説明を受けた内容を伝えあったりしました。サンクラブ多摩だより4月号にその記録が出ています。
集いの会は少人数で何でも話せる場です。どうぞ、一度覗いてみてください。
(S.T)
5月25日(土)2024年度通常総会
出席者 会員17名
昨年に続いて、今年も会員のみで通常総会を開催しました。
藤岡責任代表の挨拶のあと、59名の会員中17名出席、委任状32名で総会が成立したことが宣言され、会員の本多さんが議長に指名されて議案の審議に移りました。
1号議案の「2023年度の活動を振り返って」の中では、最初に八王子の「滝山病院事件」に対する東京つくし会の取り組みについての説明がありました。また、毎月の学習交流会については、9月に多摩市の障害福祉課長、3月に生活福祉課長をお呼びして多摩市の「障害福祉政策」や「生活保護制度」についての話を聞いたことが多摩市の実情を知る上でたいへん有効だったという説明がありました。
2号議案の決算報告では、落合代表が欠席のため、1号議案と同じ高村代表から各項目について報告がありました。運営費の支出の中で「会費分担金」の中に「草むら」が入っているが、これはどういうものか?という質問があり、それに対してグループホーム見学の際の「寄付」が正しいのだがここの項目に入れさせてもらった、という説明がありました。続いて本山監査委員からは帳簿、現金について間違いないことが報告されました。
3号議案の活動計画では藤岡責任代表から年間テーマは昨年同様の「地域で安心して生きるために」が発表されて、その裏付けとなる予算案の説明がありました。
4号議案の役員体制は、昨年度運営委員会の協力員だった上田さんが会計に加わりました。
1号議案から4号議案までそれぞれ賛成多数で承認されました。
総会終了後の懇親会では、初めに監査の松田さんから老人会で小学校や保育園に「昔遊び」に出向いているというお話と「お手玉」と「あやとり」の実演があり、堅苦しかった総会の雰囲気が一気に和みました。
その後、最近会員になった方や久しぶりに参加された方たちにひと言ずつお話してもらいました。
◎主治医とのコミュニケーションが取れなくて悩んでいる。
◎この会は、子どもを守ってあげるのではなく、子どもが自立していけるよう親が学ぶ、という姿勢に感銘した。
◎病識が無い息子で医療にも結び付かず悩んでいる。
◎娘が「のーま」のフィットネスに通っている。ほとんどのプログラムが予約制だが、フィットネスだけは予約制ではないので助かる。
◎この会に入った頃は落ち込んでいたが、自分が歌が好きだったことを思い出し、シャンソンを習いに行った。今では、一日中何回も歌って練習し、コンテストの最終まで残った。息子も私の歌を応援してくれている。
最後に発言された方は、その後シャンソンを情感たっぷりに歌ってくれました。
(S.T)
第62回高森先生の公開講演会「みんなでやろう 家族SST」 続編
この報告は、4月6日(土)に開催し、5月にHPで掲載した講演会報告の続編で、高森先生が過去に聞いた精神科医のお話から続いています。
★精神科医・臨床心理学者の北山修氏の話の続き
薬は、刺激を少しでも入れないようにするための対症療法で、夏の暑さを緩和するためにすだれを掛けるのと同じ。当事者は感覚が鋭敏で、常時、不安をもっているので、自分の心を守ることが難しい。心を守るためのオゾン層は、家族や周囲の環境によって整えていく必要があるという北山先生のお話を図にしながらのお話でした。
高森先生は、現実に起きた事件も引き合いに「当事者に家族でどう接するかが、病気の当事者にとっても家族にとっても、重要な分かれ道。家族で虐待に発展するか、困難を一緒にのりこえようとする和気あいあいの家族になるかの境」と、バザーリア先生の狂気を生まない環境とも関連づけられました。
★当時者に任せきることで息子が変わった
「全国精神障害者家族連合会」の会長をされた小松さんは、戦争中、多くの学友が戦死する中で、学徒動員の対象にならずに今生きている経験がとても苦しく、罪深く思っていたそうです。息子が病気になり引きこもっているのを見ると、若くして死んだ学友が思い出され、男の先輩として息子を指導し一人前にしなければという強い思いで息子に関わり、息子は父親を殺したいと決意したほど険悪だったそうです。
ところが、母親が亡くなり、家事のできない男同士で暮らすようになり、すべてを引きこもりの息子に任せることを決意し、文句は一切言わないようにすると、息子から「すべてを任せてくれてありがとう。今が一番幸せ」という手紙をもらうほど、関係が変わったとのこと。息子は新聞を4紙購読し、経済的にも堅実な生活を送るようになり、「財布も息子に全部預けたが、今は何も心配することはない」と言い、昨年の春に安心して逝去されたそうです。
「親亡きあと、『生きていけるの?』という言葉は、当事者にとって一番不安になる質問。これが一番のストレスのもとになる。自分自身が変わることで『大丈夫よ』と言ってあげられる親になって」というのが、先生からの言葉です。
★家族SSTについて
SSTは、戦争から帰還して麻薬依存や精神を病む患者が増大したことから、アメリカでリバーマン先生が考案した社会生活を送るためのコミュニケーションのため3技能のトレーニングのことです。3技能とは、①受信機能 ②処理機能 ③送信機能のことで、当事者たちが、なりたい自分になるための訓練で、精神疾患の再発防止や生活の質の向上に良い影響があります。
「家族SST」は、平成3年に高森先生が日本で始め、家族が理解者になることが当事者の治療にいいということで、全国へ普及活動をされています。先生が紹介されたフレーズは、「ほめることは進んでやる、悪口は言わない。家族が勉強すると、子どもが変わりやすいように、自分と未来が変わる!」ということです。
◆参加者からのお困りごと等の相談
①25歳の息子の変化
息子の具合が悪かった時、ほめるようにしたら、息子が親のことをほめてくれるようになった。その後、病気もよくなり、服薬はしているが通信制高校から大学に進学し、今は働いている。
これは相談というより、うれしい報告で、会場のみんなで拍手を送りました。
先生から、トイレに引きこもる17歳の息子の母親からの相談を受けた事例が示され、会場の参加者にどう対応するか質問があり、「安心して引こもれる場所を作ってあげる」案が出ました。不安の極みで引きこもるので、「不安な時こそ、狭いところに入りたい」という当事者の心理についての先生の説明です。別の引きこもれる場所を作る、場所が広ければトイレを別に作る、お風呂場で災害用簡易トイレを活用する等。理不尽な要求でも、物理的に解消できることには対応し、安心して引きこもれるようにしてあげることが、当事者の今を認めることであり、信頼につながるというお話でした。
②結婚後、発症した44歳の娘へ対応
結婚後、妊娠・死産を経験し発症。結婚前の若い頃に入院や服薬はしなかったが、その兆候はあったようで、婿はそれを承知で結婚した。主治医は、多剤処方で、娘もあまり信頼はしていないが、医師を変えるのには乗り気でない様子。家庭では、娘の夫が家事に仕事に頑張っているが、時々爆発してしまう。娘は自責の気持ちから「こんな人(自分)と結婚しちゃって」と言う。母親として、食事を作って持っていくなど協力はしているが、娘夫婦にどう対応したらいいのか?
結婚はストレスの第7位。もともと繊細であったところに結婚・死産を経験し、不安が大きかったことが引き金になったのでしょう。話をよく聞いてくれる主治医に変えた方がよい。 夫婦関係に親が入ってくるのが、お婿さんにとってはどうなのかの視点も必要。まずは感謝す! 夫の爆発もしょうがないと受け止め、娘さんにもそう言ってあげて。医師経由ルートで、精神障害によるヘルパー導入も考えてみてください。
③お金の管理ができない息子について
息子は障害年金2級で、6万5千円を支給されているが、たばことお酒で使い切ってしまう。どう対応したら、お金の管理ができるようになるのか?
まず、お金の使い方を年金の6万円5千円内でやりくりしてもらう。そして、食費をいくらかでもいいので家計に入れてもらうこと。年金以上のお小遣では、親亡きあとに本人が困ってしまう。「年金以上は我慢してほしい。我慢できる大人になってくれたら、お母さん、すごく助かるなぁ」とお願いしてみてください。食費も最初は少額から少しずつ増やし目標3万円を目指す。そして、できたことには、たくさんほめる。親がお断りするときは、さわやかに明るく断り、「ごめんね」をいっぱい使う。できそうなことから手を入れ始め、徐々に進めることが大事。
4月の活動
4月27日(土) 学習・交流会「保健所の仕事今むかし」
お話 南多摩保健所地域保健担当 荒井和代氏
参加者14名(会員12名)
最近暑い日と寒い日が交互に訪れ、体調不良の方も多くて参加者が少ないのではと心配でしたが、最近入会された方が早くから集まり、まずはホッとした集会でした。また年度の変わり目ということもあって講師もなかなか決まらず、荒井和代先生が承認してくださったと聞いた時には本当に安心しました。このように役員の心配の中で始まった学習会は、荒井先生の気取らない話し方のおかげで、参加者が自分の疑問を素直に出せた感がありました。
まずは簡単に荒井先生のレジュメに沿って東京全体の保健所とその中の南多摩保健所の現保健所の説明がありました。南多摩保健所は大きく庶務・医療担当の管理課、企画調整・市町村連携担当の市町村連携課、薬事指導・環境衛生・食品衛生・保健栄養担当の生活環境安全課、保健対策・感染症対策・地域保健担当の保健対策課の4つに分かれ、荒井先生は感染症対策担当として多摩、稲城、日野を担当しています。都の役割変更前は作業所や、デイケア、患者の会など都の仕事でしたが、作業所など身近なものは市役所の管轄になりました。
現在の多摩市の相談窓口は次の三か所です。
◎地域活動支援センター「のーま」
地域での生活支援と自立を図るための相談
◎地域活動支援センター「あんど」
趣味や教養の教室・水力訓練室の利用等の事業
◎相談支援多摩市障害福祉課
手帳申請、医療費助成
そのほか東京都には自治体を超えて様々な相談・医療事業があります。夜間こころの電話相談や発達相談、高次脳機能障害の電話相談など多岐にわたります。(東京都福祉保健局発行「道しるべ」参照)ざっくりと荒井先生のお仕事の概要は30分くらいで終了し、皆さんからの質問に答えて様々なお話が行き交いました。
〈治療を中断した近所の息子さんと高齢の母親の暮らし>
近所からの通報で保健所がすぐに訪問すると、当事者からは保健所は近所の人の味方=自分の味方ではない、と思われるのですぐには動けません。二人で暮らせているうちは何とかなりますが、一人残されると介入が難しくなり、生活が立ち行かなくなります。家族が元気なうちに社会との関係を作っていくことが大事です。 介護保険の範囲になると地域包括支援センターが入って何とかなる場合がありますが…。
〈精神疾患がある場合コロナで入院できる病院はありますか〉
コロナが2類扱いの時は確かに入院先が限られていて、保健所が調整していました。コロナは5類に移行した現在も流行していますが、感染者数がカウントできていません。コロナは風邪とは明らかに違う症状が見られます。
〈入院した息子のことが心配でしょうがありません〉
どこの病院も医療相談室がありますので、そこを訪ねて相談してみると良いと思います。
看護師の資格を取ってさらに一年公衆衛生の勉強をして保健師になった重さを感じさせない荒井先生のお話はリアリティーをもって私たちの悩みに答えてくださいました。
(K.H)
4月6日(土)第62回高森先生の公開講演会
「みんなでやろう 家族SST」
参加者 24名(内会員14名)
62回目を迎えたサンクラブの公開講演会が幕を開け、高森先生は、20年余りのサンクラブの歩みを振り返り、感慨深い様子で話し始められました。まず、初参加の方に挙手をしてもらい、気さくな雰囲気で話しやすいよう気を配りながら、当事者の様子を聞き出しました。遠路、江戸川区からご夫婦で来訪された参加者の方には、当事者である娘さんの状況を確認され、「夫婦でこういう会に参加して勉強すると、家中の空気が変わる。家族は何とか治してあげたいという気持ちで必死にやっているつもりでも、かなり間違ったことをやっていることが多い。3分診療と言われるように、家族が具体的にどう関わればいいのかを話してくれる医師は少ない」と、SST(Social Skill Training)が必要な訳を説明されました。相手は変えられないが、相手が変わりやすいように自分が変わることを学ぶのがSST。家族の関わり方次第で、当事者との信頼関係ができることや、逆に親から監視されるような生活では、症状が余計に悪化し、狂気を生み、家族間での悲惨な事件に発展してしまう事例があることを、複数の具体例で説明されました。
◆狂気は環境が作り出す
下記の抜粋は、高森先生がいつも紹介される、イタリア・20世紀の精神医療大改革の実践者であるバザーリア先生の言葉です。
| 狂気は、深い苦しみに裏打ちされた表現であり、また、狂気は一つの「人間の条件」であるから、医師はこの人間らしい現象にどういった姿勢で向い、どのようにその狂気の要求に応えられるか、を思うべきであるとしました。さらに「狂気は生活環境によって増長されるので、環境によって危険性を抑えることは可能」であり、病院は、狂気を増大させると非難しました。 |
狂気は、家族や仕事などの周りの環境が作り出す感情で、生活環境が変われば症状も抑えることができるという提唱です。高森先生はこれを踏まえ、統合失調症を発症する子は生まれつき敏感で、ストレスを感じやすいため、家族が子どもの現在(症状)を認め、否定しないで寄り添いながら接し、「親は味方」という思いが伝わるようにすることが大事。親が良かれと思い、次から次に助言・忠告・指導をしてしまうのは、子どもの現在を認めていない行為で、「生活環境によって狂気を増大させる」ことになります。親はつい「病気を治す」ということに精力をつぎ込みがちですが、当事者の現在を認める行為が伴わないと、ストレスを与え不安を増大させてしまいます。家を自由な雰囲気にして、当事者がのびのびとできる、安心できる、狂気を生まない環境にしてほしいというメッセージです。
◆精神科医・臨床心理学者の北山修氏の話から
高森先生は20年前に、昭和のフォークソンググループで活躍された北山修氏の講演を聞いたことがあり、印象に残った話として、「敏感」ということについて、人間の心のシステムを宇宙に例えて、次の図を描いて説明されました. (つづく)